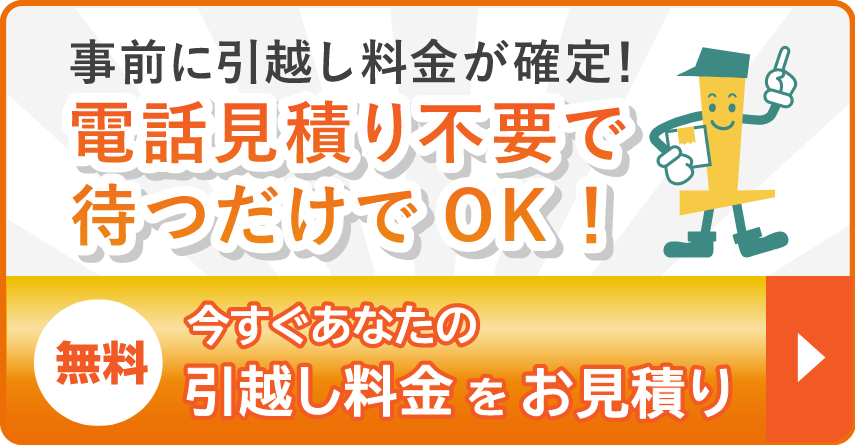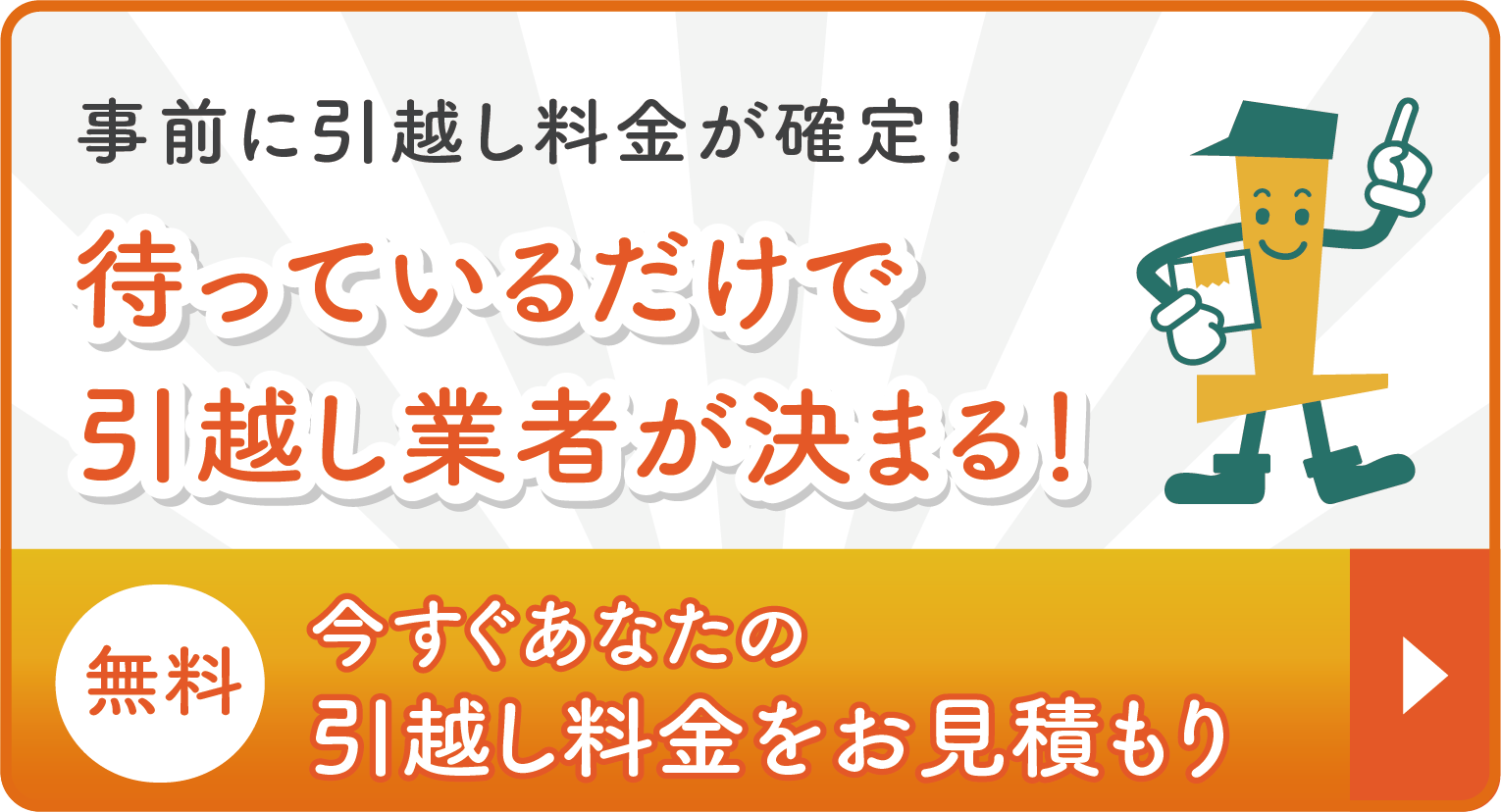- 同一市区町村内で引越すときは児童手当の手続きは特に必要ありません
- 異なる市区町村に引越すときは転出予定日から15日以内に「児童手当受給事由消滅届」を役所に提出する必要があるので注意しましょう
これまでに引越しの経験があっても、お子さんと一緒に引越しするのは初めてという方も多いのではないでしょうか。
引越し前後は準備や片付けで慌ただしくなりがちですが、子育て世帯の方はお子さんに関連する手続きの変更も忘れてはなりません。
この記事では子育てを行う上では利用されている方が多い「児童手当」の概要や手続き方法を細かく解説します。
児童手当とは?

児童手当は、中学卒業までの子どもがいる家庭に給付される手当です。
原則として、子どもが日本国内に住んでいる場合を対象としており、父母以外が養育している場合はその養育者を父母指定者とすれば指定された人に手当が支給されます。
支給のタイミングは、毎年 6月・10月・2月です。4ヶ月ごとに、前月分までの額がまとめて支給されます。支給額については後述しますが、市区町村によっては、子どもの保育料・学校給食費などを児童手当から徴収する場合もあります。
なお、申請後は申請時と異なる手続きが毎年必要です。その都度必要な手続きを確認して忘れずに行いましょう。
引越しに伴う児童手当の住所変更方法

児童手当の支給は各市区町村が行うため、引越す際にはさまざまな手続きを求められる場合があります。ここでは、引越し時における児童手当の手続きについて、引越しのパターンに分けてご紹介します。
同じ市区町村内に引越すとき
同じ市区町村内に引越すときは、転居後に役所で転居届や住所変更届を提出します。児童手当は市区町村から支給されるため、市区町村の変更がない限り特別な手続きは必要ありません。
必要書類を役所で記入・提出しましょう。印鑑や本人確認書類、マイナンバーがわかるもの等の持参も必要です。
マイナンバーの引越し手続きはこちらの記事で詳しくご紹介します。
異なる市区町村に引越すとき
異なる市区町村に引越す場合、引越し元と引越し先で2つの手続きが必要になります。
引越し元で行う手続きは期限が設けられているため、以下を確認して余裕を持った手続きを行うようにしましょう。
児童手当受給事由消滅届を提出する
まずは引越し元の市区町村にて「児童手当受給事由消滅届」を役所に提出します。
児童手当受給事由消滅届とは受給者が受給要件に該当しなくなった場合に届出が必要となる書類になります。住所が変更になることでまずは現在の市区町村の要件からは外れるため、手続きが必要となります。
役所の窓口やWebサイトなどで書類を入手、記入して提出しましょう。市区町村によっては、転出届のみの提出で児童手当受給事由消滅届が不要になる場合もあります。
なお、手続きは転出予定日から15日経過するまでに行う必要があります。役所の閉館時間などを事前に調べておき、余裕を持って提出しましょう。
児童手当認定請求書を提出する
引越し先では前述した「児童手当認定請求書」を役所に提出します。
児童手当認定請求書とは新たに児童手当の受給資格が生じたときに申請を行う書類となります。
新たな住所にて手当の受給対象となるために必要な申請となります。
先程も触れましたが、提出が遅れると手当の受給が遅れる可能性があるため注意しましょう。提出方法には窓口に直接提出するほか、郵送や電子申請が可能な場合もあります。
引越しに伴う児童手当の住所変更手続きの注意点
児童手当の申請手続きをする際、提出期限や申請者の居住地・職業などによってさまざまな注意事項があります。
「申請時に必要な書類がない」「条件を満たしていないため受給できない」などということが起こらないように、事前に確認をしておきましょう。
15日特例
基本的に児童手当は申請した翌月から支給が始まりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末付近の場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給される特例です。
例えば4月30日に子どもが生まれた場合、5月1日に手続きを行ったとします。原則に基づけば申請した月の翌月分からの支給となるため、6月分より支給されることになります。
このように、申請から受給開始までの期間が空くケースへの対策として、政府では「15日特例」を設けています。
15日特例は、出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内に申請すれば当月分から手当てを受給できる制度です。ただし、15日の期間を過ぎると原則遅れた月分の手当てを受けられなくなるため注意しましょう。
申請者が公務員の場合
原則的に、児童手当は市区町村から支給されますが、公務員の場合は勤務先から支給されます。申請場所も勤務先となるため、注意しましょう。
また、「公務員になった」「公務員でなくなった」「公務員ではあるが勤務先の官署が変わった」のいずれかの条件を満たす場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届け出や申請が必要です。
申請が遅れると原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、注意が必要です。
なお、公務員であっても派遣・出向・独立行政法人などの勤務の場合は、勤務先ではなく居住する市区町村から支給される場合があります。申請前に勤務先に確認しましょう。
単身赴任の場合
単身赴任により、子どもの居住地と手当の受給者の居住市区町村が異なる場合、受給者の転入先で申請が必要です。
必要な書類は市区町村ごとに異なるため、受給者が住んでいる市区町村に確認が必要です。なお、受給者と子どもが別居している場合は、子どもを養育していることを確認するための書類を提出する必要があるため、注意しましょう。
まとめ
この記事では、児童手当の概要や引越しの際の手続き方法、注意点などについてご紹介しました。
児童手当は子どもがいる家庭にとって非常に役立つ制度であり、子どもや保護者自身のためにもうまく利用したいものです。引越し作業と並行して児童手当の手続きを行うのは大変ですが、受給漏れが発生しないためにも手続きは早めに済ませましょう。
また、児童手当の手続きと同時に子どもの健康維持に関連する各制度の手続きも進めれば、何度も役所に足を運ぶ手間も省けます。この記事を参考に、効率よく手続きを進めましょう。